pusの記事一覧
-

2.22022
PVCラタン家具
PVCラタン(かごめ編み)家具今回はPVCラタン(かごめ編み)家具をご紹介致します。PVCとは塩化ビニル樹脂のことで、主に屋外用の家具によく見られる材料です。天然ラタンよりカラーバリエーションが多く、デザイン性に富んだ商品が数多くございます。
-

2.22022
天然ラタン
天然ラタン家具ラタンは日本名を「籐(トウ)」といい、ヤシ科の植物です。東南アジアを中心に熱帯雨林地域に生息する植物で、非常に生命力の強い史上最長の植物です。熱帯雨林地域に生息する植物ですので、通気性も良く暑い季節でも快適に使用できる素材として人気があります。
-
5.312021
事務所移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、当社は事務所を6月7日より以下の通り移転いたしますのでご案内申し上げます。なお今回の移転に伴う電話・FAXの番号変更はございません。
-

5.252021
インドネシアの新種マーブルストーン
スラウェシ島の採石場で採れる新種の大理石インドネシア中部にある島、スラウェシ島。インドネシアでは第4位の大きさを誇る島で、1949に独立したインドネシア連邦共和国の一部となり、1950年インドネシア連邦共和国はインドネシア共和国となりました。
-

1.212021
【建材のいろは】ランバーコア
反りに強く厚みのある合板ランバーコアは、ブロック状にファルカタ材を接ぎ合わせたものを心材にして合板で挟み込んだ3層構造です。ランバーコアのなかでも、表面に使用する板材の違いによって種類が異なり、「ラワンランバー」、「シナランバー」などがあります。また化粧板を貼ったものなどもあります。
-

1.202021
【建材のいろは】ガルバリウム鋼板
に耐久性に優れ、あらゆる用途に対応できる画期的な鋼板アルミ二ウムと亜鉛、シリコンを混ぜることで生まれた耐久性に優れた鋼板です。メッキ層を持つ溶融アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板を総じてガルバリウム鋼板と呼び、JIS規格では正式名称を「55%アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板」といいます。
-

1.122021
【建材のいろは】石材の種類
用途によって使い分けられる石材の種類建築に使われる石材は、大きく分けると火成岩、変成岩、堆積岩の3つに分類されます。火成岩は地中のマグマが冷えて固まった岩石で、主に「花崗岩」などが広く知られています。
-

1.112021
【建材のいろは】タイルの種類と性質
磁器質タイルと陶器質タイル床や壁、浴室や玄関などさまざまな場所で使われるタイルは大きく分けると、磁器質タイルと陶器質タイルの2種類があります。磁器質タイルは焼成温度が高く吸水しません。逆に陶器質タイルは焼成温度が低く吸水します。また、粘土の量や珪石と長石の比率はそれぞれ異なります。
-
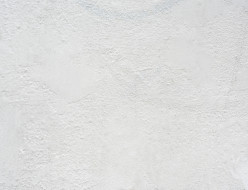
1.102021
【建材のいろは】ケイ酸カルシウム板
耐火性と耐水性に優れた無機質ボードケイ酸カルシウム板はケイカル板ともいわれています。「ケイ酸質原料」や「消石灰」、「パルプ」などの補強繊維が主原料です。ケイカル版の特徴は「耐火性」と「耐水性」です。
-
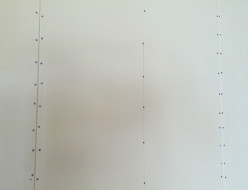
1.92021
【建材のいろは】石膏ボード
火に強く、内装材や下地材として活躍石膏ボードは、石膏を固めて板状に成型した後、表面に紙を貼りつけたものです。ローコストでありながら非常に丈夫であり、断熱性や遮音性に優れているのも特徴のひとつで。壁や天井の内装材・下地材として広く使われています。


